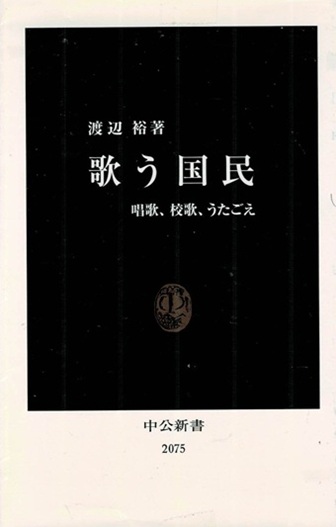
この年齢になると、かつては毎年開かれていた同窓会も縁遠くなります。そのお開きでは、定番の校歌斉唱に続けて、なんとなく唱歌の「ふるさと」を歌うことがありましたね ――都会の小学校なのに。唱歌誕生の過程にさまざまな深謀遠慮があったとは!
明治維新をへて国家を作り上げたばかりの明治政府は、西洋近代諸国の実情を知るにつけ、身震いするほどに、これらに追いつくには並大抵の努力では、とてもできないと思ったのでしょう。国家力の向上のために、国民生活のあらゆる局面に口を出すように務めたのです。
唱歌もその一端を担いました。異形かつ巨大な西洋文化との間にどのように関係を作ってゆこうかと、明治の先人たちは知恵をしぼった。その結果、西洋音楽の導入をはかり「唱歌」なるものを編み出し、国民国家形成のプログラムを作り上げた。国際社会に打って出ることを決断した日本にとって、「国民」意識の確立はむずかしい問題だ。まさにその場面で音楽が必要とされた。決して芸術などではなく、近代国家の構成員としての国民の身体や精神を作りあげる、ツールとしての役割だ。
音楽の中心は合唱文化だった。原型は「フランス革命」ですね。そこでは合唱が連帯感を生み出し大きな役割をはたした。19世紀は合唱運動がヨーロッパ各国で大きな盛り上がりをみせた時代だった。皆で一緒に歌をうたうことが、意識確立の最も有効な手段考えられたのだ。
唱歌は「国民づくり」のための切り札だった。尋常小学唱歌には、故郷、春の小川、朧月夜…などがあった。最初はまだ日本人の作曲したものは採用できなかった。イギリスやドイツの歌曲を原曲とするものが多く含まれていたが、歌詞は原詞とは似ても似つかぬ道徳的なものに変えられていた。
西洋モデルの思想や制度に次々と出会って国民はとまどう。それらを少しでも早く修得するように、新しい制度の趣旨や利点などを歌にして覚えさせるために唱歌もいろいろ作られた。郵便貯金唱歌がそうですね。小銭を地道に貯めることの大切さを説き、郵便局にあづけましょう、という具合だ。
日本人は、明治以前には「ナンバ歩き」だった。号令にあわせて一斉に同じ動作をするような「近代的身体」を持っていなかった。軍隊とか工場では必須ですね。このため唱歌とともに、遊戯が教育上最も重要な役割を担わされた。モデルはドイツの幼児教育法。ラジオ体操だってそうだ。簡易保険局の肝いりで始められたが、もともとはアメリカの保険会社の例。国民の健康増進によって加入者の死亡率を下げることをねらったものだ。
小学校内で歌われる唱歌はすべて文部省の認可が必要とされた。校歌などのコミュニティソングを国民歌謡として位置づけるという考え方が明治政府にはあった。しかし特に戦後、社会のあり方が大きく変わっていく中で、校歌は相変わらず存在感を保ったが、最近では、シンガーソングライターなどに制作を委嘱するケースも増えている。横浜市立倉田小の校歌はシンガーソングラーたー白井貴子の作詞・作曲によるものだ(1988年)。
◆『歌う国民 唱歌、校歌、うたごえ』渡辺裕、中公新書、2010/9月