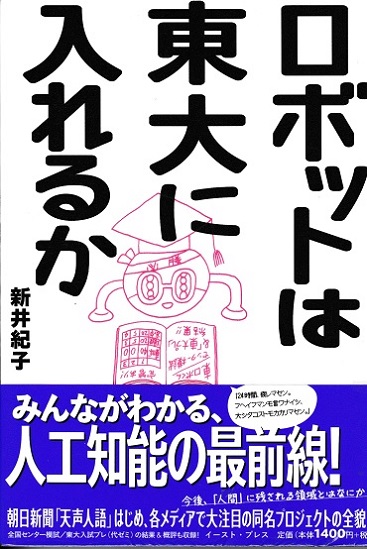
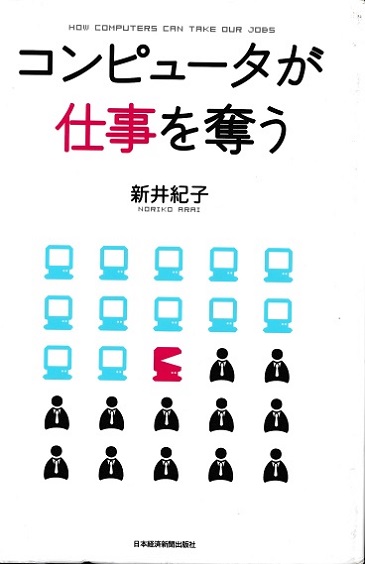
いまや株取引の7割はAI(人工知能)がサポートしているとか。AIが現実社会と密接なつながりを持ち始めたとの実感がある。いま、数学者・新井紀子さんの著作を読んでいるのだが、――『ロボットは東大に入れるか』や『コンピュータが仕事を奪う』など。AIに備えての、教育への提案が示唆に富んでいる。
「ロボットは東大に入れるか」のプロジェクトは、人間の人間たるところとはいったい何なのか、それを、どうしても知りたかったとのこと。ロボットならば、なんなく東大に入れるだろう、というのが世間の常識か。ところが、英語のリスニング問題は残念ながらさんざんな結果だった。というのは、解答の選択肢がイラストだったからなのだ。バースデイ・ケーキに、どうやってブルーベリーを飾り付ければいいかなという問題。ブルーベリーがのったデコレーションケーキなんて初めて見るものだろう。なのに、われわれ人間には、イラストが正しくわかる。一方のコンピュータは苦手だ。
犬と猫の写真の区別であれば、たくさんのデータがそろえば学習のしようがある。ところが、イラストはなかなか難しい。写真と違ってイラストは、人の脳という、複雑なしかけを通って出力される。写真に比べるとものすごくバラつきが大きいからなのだ。
AIの実現方法には2つある。帰納と演繹だ。1990年代、情報科学の多くの分野では、新しい方法――機械学習と呼ばれる方法論に取り組み始めた。例えば、犬と猫の判別課題であれば、「猫とは何か」を定義することはしないでブラックボックスとする。人間がこれは猫だと判断した画像を大量に取得して、統計的な特徴によって猫らしさをとらえるのだ。過去の存在しているデータから、まあこんなもんだろう、という統計的な判断をする。「なぜ正しいのか」ということをコンピュータにわかっているわけではない。いままでこういうふうだったからおそらくこれからもそうだろう、という話だ。
翻訳の分野では、ルールベースつまり演繹型の自動翻訳に対して、グーグル翻訳のような、AI型の自動翻訳システムが現れた。各言語で書かれた文とその翻訳を大量にコンピュータに学習させ、その上で統計的に正しそうな訳文を出力するのだ。演繹型翻訳では各言語を熟知し、その文法をルールとして抜き出す必要があり、莫大なコストがかかる。一方、グーグル翻訳では同じ文の訳を集めて、統計的に妥当性が高そうな文を表示すればよいだけのこと。多くのユーザが使いフィードバックを加えることによって、さらに翻訳の精度は上がっていく。
AIの核となる機械学習によって得られるのは「こんな条件のときには、こうするとよい」という経験則の蓄積でしかない。自ら体験することを通じて帰納を獲得する段階にある年齢の子どもたちにとっては、コンピュータが思考の芽をつんでいないかとの懸念がある。動画による受動的な学び、表計算ソフトに頼った計算やデータ処理は阻害要因だろう。
教育が大きな課題だと著者はいう。「ふつうはそうする」「みんなそうしている」というパターン認識に基づく、ルーティンのことしかできない人を、教育が大量に育成していくのであれば、AIによって仕事を奪われるだろう。パターン認識では達成できないタイプの課題を学校で意識的に増やしていくこと。あるいはパターン認識で発見したことに対して、なぜそのようになるかの理由を言語化することを求める教育が必要だ。
論理的に考えさせること、言語化させることが大切だ。「なぜだと思う」と聞き返すこと、作業の手順を隣の子に説明すること、道順を図にすること、いまわかったことをノートに論理的に書くこと、……等々。
長時間かけて自然を観察したり、実験したりしながら物理や生物の仕組みや法則を体験して脳の中で概念構築を促すこと。これが大切だろう。教師と子どもは、互いに耳を澄ますことで意味をわかりあうことが重要。耳を澄ます、という能力こそが、コンピュータに対して私たち人間が勝てる分野なのだ。
◆ 『ロボットは東大に入れるか』 新井紀子、イースト・プレス、2014/8
◆ 『コンピュータが仕事を奪う』 新井紀子、日本経済新聞出版社、2010/12