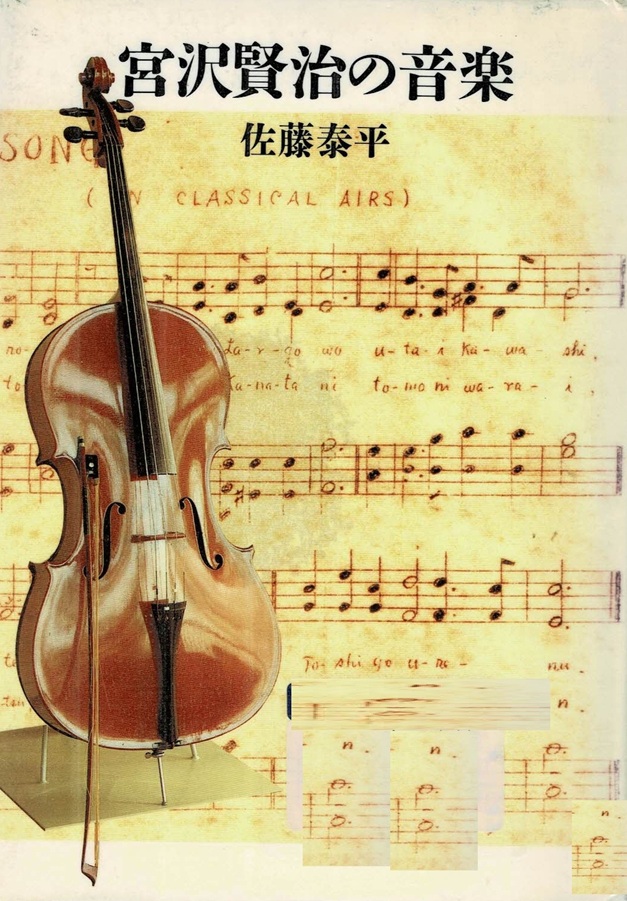
宮沢賢治の童話は百編を超える。その3分の1に歌が入っている。無理をして歌わせているのではない、自然の中に存在するものたちの訴えやつぶやきを、そのまま伝えているのだ。
「銀河鉄道の夜」では、楽章が明記されずに「新世界交響楽」が聞こえてくる場面がある。賢治はドヴォルジャークの音楽を読み手に想起させる。
「星めぐりの歌」は、賢治が作詞・作曲した中でももっとも広く知られ、歌われている曲だどろう。童話「双子の星」の2人の童子が一晩中、銀笛を吹く曲だ。
花巻農学校の生徒のために歌曲を作ったりしている。「角礫行進歌」というマーチを作詞して生徒に教えている。この行進曲は、グノーのオペラ『ファウスト』の「兵士の合唱」の曲に詩をつけたもの。
賢治の周辺には音楽がいっぱいあった。自身が収集したレコード、親友の藤原嘉藤治のレコードや楽譜、無声音楽の楽士たちによる伴奏音楽、浅草オペラ、賛美歌…。賢治をそれらたくさんの音楽を歌ったり、聴いて楽しみながら使えそうなものを探していたのである。
賢治の豊かな音楽性に築いた最初の人はおそらく,賢治の母・イチだった。それに弟・清六さんだ。藤原嘉藤治さんは花巻高等学女学校の教諭で亡くなるまで親友だった。
賢治は一生を通じて音楽と強くかかわりを持ち続けた。レコードの収集や鑑賞、加えてレコード・コンサートを自ら主催し解説までした。また、既成の曲に作詞したり自作の詩に作曲したりした。自作の詩を朗読するときには、それに合わせて友人に即興でピアノを弾かせた。楽器を買い集め農民による小オーケストラの企画までした。賢治はこれらの幅広い音楽体験の中で学び得たすべてを、たくさんの作品に注ぎ込んだ。
とくに「セロ弾きのゴーシュ」は音楽自体が物語りの重要な構成要素になっている。金星音楽楽団の困り者であったゴーシュが動物たちの力をかりて、たった6日間で上達してしまという筋書きだ。
金星音楽団の特別音楽会が企画され、曲は第六交響曲であった。
ゴーシュは金星音楽楽団の一員であった。あんまり上手でないセロ弾きという評判だった。ゴーシュは口をりんと結んで練習に励む。指揮者を見たり、他の楽器の音と合わせて、弾くという余裕がない。ただ一心に弾きまくる。自分のリズムで皆についていくだけなのだ。楽長が厳しく指摘する。「いつでも君だけとけた靴のひもを引きずって みんなのあとをついて歩くようなんだ」。叱られ皮肉られる。
動物たちがゴーシュを訪ねてくる。猫の目的はゴーシュをからかいに来たのではない。子守歌のような靜かでおだやかな音楽を聞くためだ。野ねずみのお母さんから、楽長からは一度も聞いたことのない「上手」というほめ言葉を聞いた。ゴーシュを訪ねる動物は、それぞれが内容の違う音楽でゴーシュと交流した。
賢治のSPレコード収集はかなり凝っていた。交響曲だけでも、ベートーヴェン、シューベルト、ブラームス、チャイコフスキー、ドヴォルジャークなどの作品を聴いていた。ベートーヴェンの第1番から第9番まで全部をそろえていたようだ。とりわけ第6番「田園」を好み、第2楽章の幽玄ともいえる美しい主題には作詞までした。
昭和20年8月10日の花巻空襲の時、賢治の生家も焼け、清六さんたちが必死で賢治の原稿などを守った。SPレコード12枚入りのレコードアルバムをそのとき持ち出した。焼失を免れ偶然残された12枚のレコードは確かに賢治の遺品には違いないが、賢治が清六さんのために特別に選んで遺したものとだと思いたい。これらの興味深い12枚のレコードは現在、花巻の宮沢賢治記念館に展示されている。
―― 賢治遺品レコード、宮沢清六に遺したレコード
(1)交響曲第六(田園)(ベートーエン)H.フィッツナー指揮、伯林国立歌劇場管弦楽団 Pol.40056-61、6枚、1927年9月、15円
(2)「オルフェオとオイリディケ」(グルック)R.へーガー指揮、伯林国立歌劇場管弦楽団、Pol.40061のB面
(3)「未完成交響楽」(シューベルト)O.クレンペラー指揮 ベルチン国立歌劇場管弦楽団、Pol.40032〜4、3枚、1929年7月、7円50銭
(4)「ドン=ファン」(R・シュトラウス)A.コーツ指揮、交響管弦楽団、V55176〜7,2枚
(5)「前奏曲『牧神の午後』」(ドビュッシー)A.ヴォルフ指揮、巴里コンセル・ラムルー管弦楽団Pol.40412,1枚
◆ 『宮沢賢治の音楽』 佐藤康平、筑摩書房、1995/3